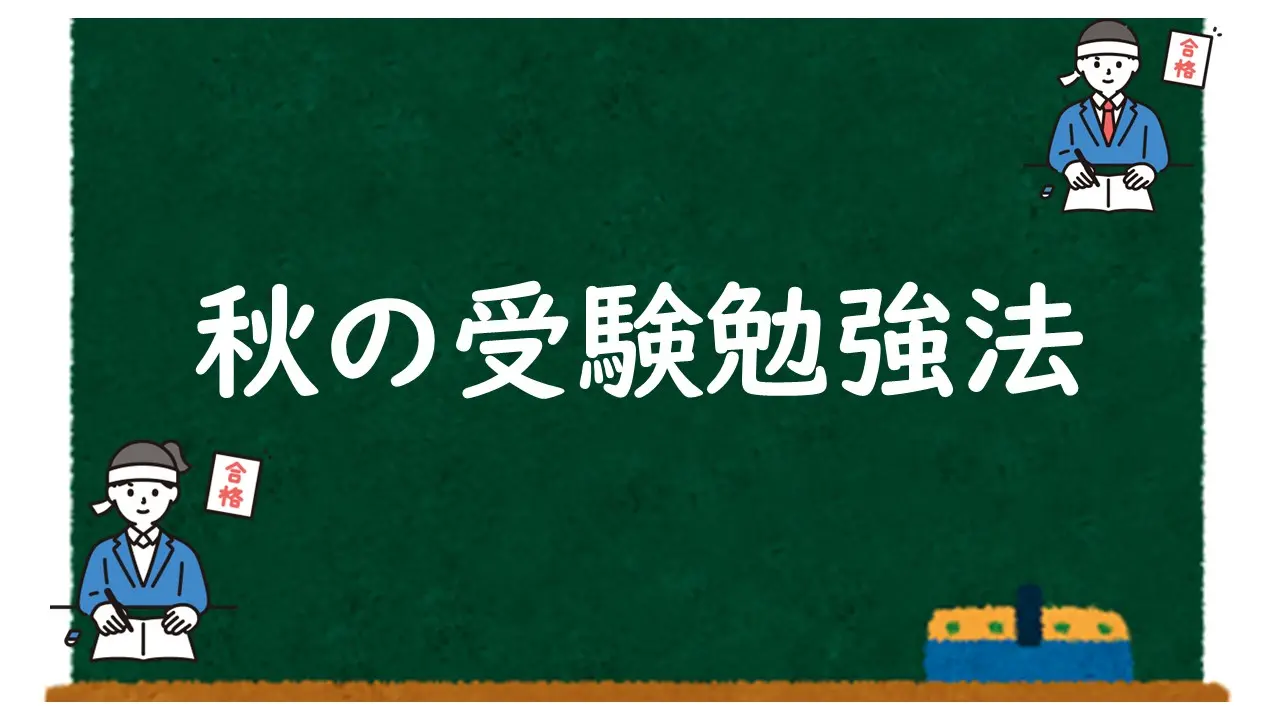
秋は、中学・高校・大学受験のいずれにおいても、受験生にとって非常に重要な時期です。この期間にどう勉強するかが、合格の行方を大きく左右します。今回は、9月から12月にかけて、各入試段階でどのような勉強法を取り入れるべきか、解説していきます。
中学入試:基礎固めから実践へ
中学入試の9月から12月は、応用力と実践力を身につける時期です。夏休みまでに習った内容の定着度を確認し、苦手な単元を徹底的に克服しましょう。
9月~10月:弱点克服と応用問題
まずは、これまで解いた模試や問題集を振り返り、点数が伸び悩んでいる単元を特定します。算数なら「速さ」「割合」「図形」、理科なら「てこ」「電流」など、つまずきやすい分野に絞って復習し、類題を繰り返し解いて、応用問題にも対応できる力を養います。
11月~12月:過去問演習と時間配分
11月からは、志望校の過去問演習を本格的に始めましょう。過去問は、ただ解くだけでなく、本番と同じ時間で解くことが重要です。時間内に問題を解き終える練習をすることで、時間配分の感覚を掴むことができます。また、解き終わった後は、正解・不正解にかかわらず、すべての問題を見直し、なぜ間違えたのか、どうすれば解けたのかを分析します。特に、国語の記述問題や算数の途中式など、部分点をもらえる問題では、どのように記述すれば点がもらえるのかを意識して練習しましょう。
高校入試:内申点と入試対策の両立
高校入試では、入試本番の点数だけでなく、中学3年間の内申点も合否に影響します。大分県では30%がない進展となっています。そのため、9月から12月は、定期テストと入試対策を並行して進める必要があります。
9月~10月:定期テスト対策と基礎固め
この時期は、2学期の定期テストが内申点に大きく関わるため、しっかりと対策しましょう。テスト範囲の教科書や問題集を繰り返し解き、暗記科目は毎日少しずつ覚える習慣をつけることが大切です。特に、主要5教科(国語・数学・英語・理科・社会)の得点アップは、学力テストの点数向上に直結します。
また、夏にやりきれなかった1・2年内容がある場合は、このタイミングで早めに補っておきましょう。
11月~12月:入試実践問題と私立・公立対策
定期テストが終わったら、入試本番を意識した問題演習にシフトします。まず、志望校の過去問を解いて出題傾向を掴みましょう。私立高校を併願する場合は、公立高校とは異なる出題傾向に対応するため、それぞれの対策が必要です。私立は単元ごとの深い理解を問う問題、公立は基礎的な知識を幅広く問う問題が多い傾向にあります。
この時期は、苦手科目の克服に加えて、得意科目をさらに伸ばすことも重要です。得意科目で確実に点数を稼ぐことで、全体的な合格率を上げることができます。
大学入試:共通テストと二次試験のバランス
大学入試では、共通テストと二次試験(個別学力試験)の両方で高得点を取る必要があります。9月から12月は、両試験に向けた戦略的な学習が求められます。
9月~10月:二次試験対策+共通テスト対策の本格化
11月からは、共通テストの演習を続けつつ、二次試験対策にも徐々に力を入れます。二次試験は記述式が中心となるため、論述問題や証明問題など、自分の言葉で解答を作成する練習が重要です。志望大学の過去問を解き、出題傾向や難易度を把握し、必要な知識や記述力を補強します。共通テストと二次試験の配点比率を考慮し、どちらにどれだけの時間を割くか戦略的に計画を立てることで、効率的な学習ができます。
11月~12月:共通テスト対策(二次試験対策)
共通テストは、マーク式の問題が多く、時間内に効率よく解く練習が不可欠です。この時期から、共通テストの過去問や予想問題を繰り返し解き、問題形式に慣れるとともに、時間配分の練習を始めましょう。特に、複数の資料を読み解く問題や、思考力を問われる問題に時間をかける練習が必要です。
余裕がある人は引き続き2次試験対策も引き続き取り組みましょう。
まとめ
9月から12月は、自分の現在地を正確に把握し、目標に向かって計画的に学習することが何よりも重要です。模試や過去問の結果を分析し、弱点を見つけて補強することで、着実に実力を伸ばすことができます。 私たち個別指導塾は、一人ひとりの学習状況や目標に合わせた最適な学習プランを提案し、合格までを徹底的にサポートします。この秋、一緒に頑張りましょう。応援しています!


